2025.03.18
レゾナックに学ぶ「企業変革」と「人的資本経営」
—エグゼクティブコミュニティ会員限定のスピーカーズイベントを開催

パーソルキャリア エグゼクティブエージェントでは、各領域でご活躍の経営層や次期経営層を対象に、さまざまな形態で「パーソルキャリアエグゼクティブコミュニティ」を運営しています。
ファイナンス領域のエグゼクティブを対象としたCFOコミュニティ、HR領域のエグゼクティブを対象としたCHROコミュニティもそうした取り組みの一つ。これらのコミュニティでは、新たなビジネスネットワークづくりや情報交換を目的としたスピーカーズイベントを定期的に開催しています。
2025年3月には、当エグゼクティブコミュニティの会員限定、初の対面イベントとして株式会社レゾナック・ホールディングスCFOの染宮秀樹氏をお招きし、CFO・CHRO合同の対面イベントを実施しました。


2023年1月1日、昭和電工と昭和電工マテリアルズ(旧日立化成)が統合し誕生したレゾナック・ホールディングス。
CFOに就任した染宮氏は同社を「稼ぐ力のある企業」にするため、収益性変革やポートフォリオ変革などを推進。ファイナンス戦略のみならず、変革を実現するためのCFO組織づくりや次世代育成、
組織風土改革などにも取り組んでいます。
染宮氏はどのようにして変革を進め、企業価値向上につなげているのでしょうか。
この記事では「ファイナンス戦略/経営戦略と人的資本経営」をテーマに行われた染宮氏の講演内容や、盛況の中で新たなつながりが生まれた懇親会の模様をダイジェストでお伝えします。
ゲストスピーカー プロフィール 株式会社レゾナック・ホールディングス 取締役 常務執行役員 最高財務責任者(CFO) 染宮秀樹氏
1990年野村総合研究所 企業財務調査室入社。1997年野村證券金融研究所副主任研究員。
1999年メリルリンチ日本証券、2009年JPモルガン証券にてテクノロジー・メディア・テレコム部門の責任者を歴任。
2015年ソニー(現ソニーグループ)に入社し、副社長CFO付チーフファイナンシャルストラテジストとしてグループ全体のM&A責任者を務める。
2016年ソニーセミコンダクタソリューションズを経て、2021年ソニーCFO付特命担当。2021年昭和電工(当時)に入社、グループCFO準備室長。
2022年同取締役常務執行役員 最高財務責任者(CFO)。2023年より現職。
迷ったときは「よりアドレナリンが出る道」を選ぶ
染宮氏:まずは自己紹介を兼ねて、私自身のキャリアに対する考え方をお伝えできればと思います。

私はビジネスキャリアを歩む上で、常に「アドレナリンカーブ」を重視してきました。キャリアの中ではポジティブなこともネガティブなこともいろいろと経験します。
そうした経験を通じて得た人生における累積アドレナリン分泌量を、歩んできたキャリアと重ね合わせていく考え方です。
アドレナリンがほとばしっていて仕事が楽しいときは、アドレナリンカーブが上がっていきます。逆に何かに失敗して落ち込んだときには、カーブが下に向かっていくのです。
私の場合は、これまでに7回大きな失敗をしてきました。一つひとつの失敗はネガティブな出来事かもしれませんが、その経験が糧となり、新たなアドレナリンカーブの上昇局面に向かうこともありました。キャリア全体を見れば金融業界が長いものの、当時のアドレナリンカーブよりも、事業会社に来てからのほうがダイナミックに変動していますね。
今は、これまでのキャリアで最も1日あたりのアドレナリンの分泌量が多いと感じています。
私が考える働くモチベーションとは、「生涯アドレナリン分泌量の最大化」。
キャリア選択に迷ったときは、よりアドレナリンが出る道を選ぶ。そんなふうにして歩み、現在のレゾナック・ホールディングスでの役割につながっています。
「典型的なJTC」だった2社の統合で目指したもの
染宮氏:続いては私がCFOを務めるレゾナック・ホールディングスについて紹介します。
最近では、伝統的な日本企業を指す「JTC」(Japanese Traditional Company)という言葉がよく聞かれるようになりました。
当社の前身である昭和電工と日立化成はともに100年以上の歴史を持ち、従業員のほとんどをプロパー社員が占める、まさにJTCでした。
しかし、合併の意思決定とその後の展開では、およそJTCらしからぬ道を歩んでいます。
レゾナック・ホールディングスは、買収対象となる企業のキャッシュフローを返済原資として金融機関からの借り入れを行うLBO(レバレッジド・バイアウト)ローンを活用し、
小(昭和電工)が大(日立化成)を買収するというリスキーな形で誕生しました。
昭和電工には大手化学メーカーとしての豊富な実績があり、分子レベルから化学素材をつくる「川上」の分野に強みがありました。
一方、日立化成は材料をもとにして半導体など成長分野の製品をつくる「川中」の事業を得意としていました。両社の強みを合わせ、世界トップクラスの機能性化学メーカーを目指すことを企図したのです。
経営の在り方も、従来のJTC的なそれとは一線を画す覚悟を持っていました。統合によって第二の創業を果たし、従業員2万6000名のスタートアップをつくる。
そんな思いで現経営チームが発足した際には、合併前の両社の執行役員32名のうち24名が外れました。ちなみに私自身はこのタイミングで仲間入りしています。
「チーム髙橋」で描く、新たな理念と成長戦略
染宮氏:この新たな経営陣によるチーム経営体制は、レゾナック・ホールディングスのユニークさを表していると思います。
CEOの髙橋秀仁は長期的課題である文化醸成や共創型人材育成にフォーカスし、それ以外の領域は各役員陣に大胆に判断を委ねているのです。
第二の創業にあたっては、この「チーム髙橋」組成による執行体制の再編成が重要な意味を持っていました。
髙橋はCEO就任を受諾する際、「自分が社長をやるなら自分で経営陣を選ぶことが絶対条件」だと指名諮問委員会に突きつけ、認めさせたそうです。
そして前述の通り、旧2社の32名のうち24名の執行役員を外し、私を含め、外から来た4名を加えた計12名でチーム髙橋を組成しました。
一般的に日本の大企業ではライバル同士が出世街道を争い、誰かが社長に就任すると別の誰かは部下になります。結果的に新たな執行体制となっても役員同士が気を遣い合ってしまい、意志決定の遅れにつながることもあります。
チーム髙橋にはそうした組成の経緯がないため、言いたいことをフラットに言い合える関係性があるのです。
また、新たな執行体制が発足した後には、まず役員同士が自己開示をして相互理解を深める場を持ちました。それがチーム髙橋の心理的安全性につながっています。
新たな体制のもとで私たちは経営理念を再構築し、「化学の力で社会を変える」というパーパスを掲げました。その上で4つのバリューを定め、組織づくりの礎としました。
次に取り組んだのは新たな成長戦略の策定です。2030年にどんな企業になっていたいかを徹底的に議論し、「世界と戦って勝ち、サステナビリティに貢献する企業」「共創型人材を創出する企業」になると決めました。
そのための事業展開として、半導体材料領域に一気にシフトして経営資源を集中させることも決定しています。

4.ポートフォリオ改革でバランスシート改善へ
染宮氏:私自身はCFOとして、バランスシート改善を使命として動き出しました。
レゾナック・ホールディングスはLBOによる買収からスタートしています。当然ながらバランスシートは大幅に悪化していたのです。
半導体材料領域へ集中投資するにあたり、まずはポートフォリオ上の事業位置付けを再カテゴライズしました。
安定収益事業は減価償却の範囲内でしか投資しないこと、営業キャッシュフローやリソースをコア成長事業にシフトさせること、
全社員が企業価値向上のリターンを得られるように株式報酬の制度を見直すことなどを決め、打ち手を施していきました。
ポートフォリオ改革では、3つの原則を置いています。
「会社全体の戦略に適合するか」「採算性と資本効率は最適か」「私たちがベストオーナーなのか」(私たちよりもっと会社を良くできるオーナーがいればその人たちに渡した方が従業員はハッピー)の3つです。
この考えに基づき、これまでに13事業を売却。さらには本社ビルなどの資産も売却し、3年間で少しずつバランスシートの改善が進んでいます。
次世代を担う共創型人材を増やしていくために
染宮氏:レゾナック・ホールディングスは従来の総合化学メーカーから機能性化学メーカーへ進化することを目指しており、
そのためには共創型人材が必要だと定義しています。共創型人材をなるべく多く増やしていく経営が、私たちなりの人的資本経営なのです。
「化学の力で社会を変える」というパーパスと、パーパス実現に向けたバリュー。このメッセージを浸透させるために、私をはじめ、
ビジネスユニット長たちがたくさんの現場を回って発信しました。
聞いた人たちがどう受け止めたのかを確認するために、双方向の対話も続けています。
2022年から始まった「モヤモヤ会議」(ラウンドテーブル)もそうした取り組みの一つ。CEOが各事業所を回り、現場の社員が抱えているモヤモヤを話してもらうのです。
そこで出た意見に対しては、CEOと事業所長が一緒にいるその場で意志決定していきます。この会議は実に年間110回にわたり行われています。
2023年から2024年にかけては、社員それぞれに個人のパーパスを考えてもらい、会社のパーパスとどのようにつながるかを各事業所で議論しました。
また、サーベイの質問項目とスコアを分析した結果、働きがいを向上させるには心理的安全性を高める対話が重要だという因果関係が見えてきました。
そこで現在は1on1の取り組みも強化しています。
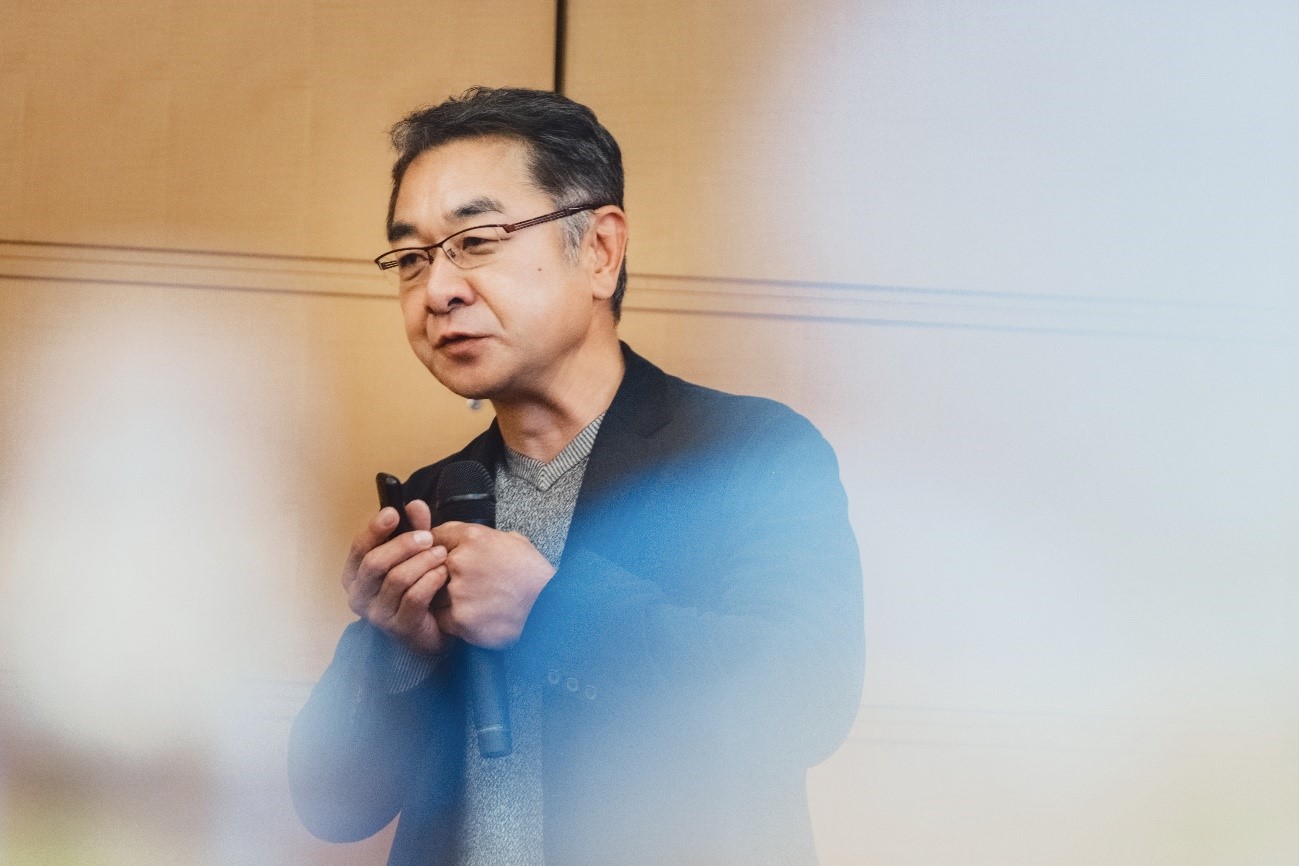
こうした取り組みの結果、エンゲージメントスコアは3年前の51%から直近では57%へ上昇。「心理的安全性や成長機会がある」と感じる社員が増えています。
風土改革を徐々に進めながら、社員にバリュー体現を促す人事評価制度を構築し、次世代のリーダー人材を選定・育成するサクセッションプランも展開。
私自身は「染ラボ」という次世代リーダー育成(社内MBA)プログラムを開講しています。コーポレートファイナンスは私が、
マーケティングストラテジーは別の講師が担当し、7カ月の講義を経て、次の5カ月でレゾナック・ホールディングスの戦略を考えてもらうプログラムです。
ここに参加する社員の平均年齢は35歳。まさに次世代経営人材です。日常業務から離れて自社の経営戦略を考えてもらい、
「レゾナック・ホールディングスのリーダーになることが、最もアドレナリンの出る道だ」と思ってもらえるようにしたいと考えています。
企業変革ストーリーに刺激を受け、エグゼクティブ同士の新たなつながりも
染宮氏の講演に続く第2部では、立食パーティー形式の懇親会を実施しました。 懇親会では、それぞれのテーブルで参加者同士が自己紹介。自由に情報交換や歓談を楽しんでいただくとともに、第1部での染宮氏の講演を受けた質疑応答の時間も設けました。


参加者からは「染宮さんのお話から大いに刺激を受け、貴重な機会となった」「日本企業でこうしたドラスティックな改革が進んでいることに驚いた」といった感想が寄せられました。
また、女性CFOや女性CHROが多く参加していたこともあり、「女性役員同士の新たなつながりが生まれた」という声もありました。
質疑応答における参加者からの質問と、染宮氏の回答の一部も紹介します。
Q.新しい経営チームでは、どのようにして関係性を構築したのでしょうか?
染宮氏:チーム髙橋をつくったときに最初に行ったのは、米マイクロソフトCEOのサティア・ナデラさんが行ったような「それぞれのライフヒストリーを共有する」取り組みでした。
当時参加していた12名全員の人生を共有し、質問し合い、相互理解を深め、心理的安全性が本当に高まる場となりました。
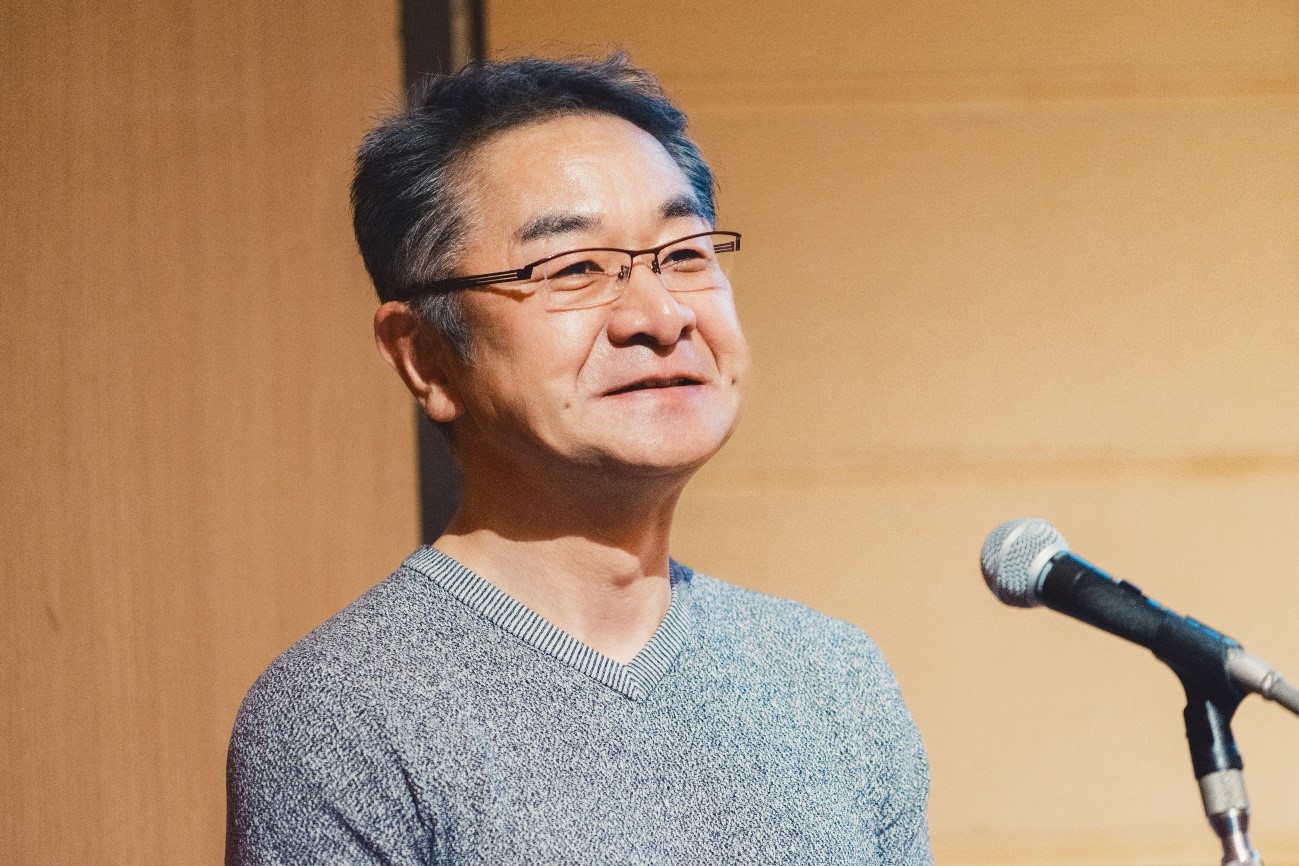
Q.変革を加速させるための人材育成で力を入れていることは?各企業にオーダーメイド化したコンサルティングをしています。
染宮氏:私たちが大切にしているバリューを特に体現している社員には、社長表彰とプレゼンの場を設けています。
また、私が開催する「染ラボ」に参加しているコアメンバーは、それぞれの職場でインフルエンサーとなって活躍してくれています。
社員によるこうした主体的な動きを支え、賞賛していくことが、組織風土改革には欠かせないと考えています。
終盤には、エグゼクティブエージェントを運営するパーソルキャリア EAS事業部より、事業部長の木村浩明があいさつに立ちました。
「ビジネスの最前線で活躍されている方々が日々刺激を得られるよう、エグゼクティブコミュニティのネットワークを築き、拡大してきました」と振り返る木村。
転職支援を主務とするエージェント事業の枠を超え、これからも経営に向き合う方々を応援していきたいという決意を新たにしていました。
***
約30名のエグゼクティブコミュニティ会員が参加した今回のイベント。染宮氏へ個別に質問を投げかける参加者も多く、 自社の変革や人的資本経営に向けたヒントを得られたようです。その後も続いた懇親会ではそれぞれがテーブルを移動し合いながら交流を深め 、新たなつながりが生まれる場となりました。
